|
恋とウーロン茶
パラパラと雑誌をめくっていた和谷の手がふと止まった。
「ねえ、伊角さん。ほら、これ。この前見たいって言ってたやつじゃねえ?」
声をかけると、テーブルをはさんだ向かい側で本を読んでいた伊角が顔を上げた。
表情を隠していた前髪がサラリと横に流れ、現れた黒い瞳と視線が交わる。
それだけで、胸がドキリとした。
そのままテーブル越しに見せればすむのに、わざわざテーブルを回りこんで伊角のすぐ隣に移
動する。
やっとつかんだきっかけを無駄にするわけにはいかなかった。
最近何かと時間が合わなかった二人にとって、今日は久しぶりの二人きりの夜だ。
和谷は嬉しくて嬉しくて会う前からそわそわしていた。
だが、部屋に上がるなり抱きついてしまいそうになるほど舞い上がっていた和谷に対して、外
で会う時と全く変わりないように見える、この年上の恋人。
買ってきた夕食を食べ終わった今も、気がつけば何故か読書の時間になってしまっていた。
当然和谷は本など読む気分ではなかったのだが、こうもストイックな顔を目の前にしては黙っ
て従う他はない。そういうコトしか頭にないと思われるのも嫌だった。
意識は向かい側にばかり向きながらも何気ない顔をして雑誌のページを繰っていた。
隣に行きたい。──その体温に、触れたい。
テーブル一つ分の距離さえもどかしかった。
そしてやっとつかんだきっかけ。
「ん、どれ?」
伊角は自分の方の本を閉じ、身を乗り出すようにして隣に座った和谷の手元を覗き込んだ。
肩が触れる。
「あ、ホントだ。どこの映画館でやってんのかな」
すぐ目の前で、長い睫毛が上下していた。
走り出す鼓動に、雑誌を持つ和谷の手に力が入る。
和谷が一人暮らしを始めて以来二人で過ごせる夜は増えたけれど、それでもこのドキドキする
気持ちは少しも衰えをみせなかった。
否、前より色々な表情を知ってしまった今の方がイヤでも加速してしまう。
とある夜の伊角の姿を思い出しそうになり、慌てて頭の中から追い払った。
ついつい襟元にいってしまいそうになる視線を無理矢理雑誌のページに向けながら、和谷はふ
と思いついた計画に声を弾ませた。
「ね、伊角さん。今度の金曜の夜、これ一緒に観に行かない? 確か予定なかったよね?」
「あ、ゴメン。その日用事入っちゃった」
当然色好い返事が返ってくるものと決め込んでいた和谷は、伊角の答えによろけそうになった。
「ええ!? 何の用事!?」
「九星会のみんなが俺の誕生祝いやってくれるって」
「……」
九星会を辞めてから1年以上経つ今でも、伊角が彼らにどれだけ可愛がられているかは和谷も
よく知っていた。棋力を見込まれてという理由だけではもちろんない。
ある時「伊角さんってみんなから愛されてるよね」と言ったら「それは和谷だろ」と笑われて
しまったが。
伊角は皆から愛されている。
それは喜ばしい事実であり、誇らしくも思えるのだが──それでいてほんの少し、不安を誘う。
「何時ごろ? 何処で?」
「7時に新宿の津田屋。紀伊国屋の裏の方の」
「……飲むの?」
ダメだと思いつつ、声が低くなる。
伊角はそんな和谷にちょっとだけ不思議そうな顔をした。
「うん、たぶん。一応ハタチのお祝いだって言うからには飲まされるんじゃないのかな」
「…ふーん」
気のない返事に、伊角が笑った。
「大丈夫だよ。イッキ飲みなんてしないから」
そうじゃなくって、と言いかけてやめる。
プロ試験に受かってからというもの、伊角が酒を飲む機会が増えた。
合格祝いだ免状授与祝いだのと、ちょくちょく呼び出しがかかる。
特に中学、高校時代の友人たちは伊角のプロ試験浪人が終わるのを待っていましたとばかりに
誘いをかけてきていた。「みんな試験終わるの待っててくれたんだよ」と嬉しそうに微笑む伊角
に、それなりに複雑な想いがよぎる。
和谷の知らない、学校での伊角を知っている彼等。「飲み会」という言葉が日常に組み入れら
れる彼等にいやでも感じてしまう、年齢の差。
そして何より…
「和谷? どうかしたのか?」
黙り込んでしまっていた和谷がはっとして顔を上げると、すぐ目の前に心配そうな顔があった。
鼓動が跳ねる。
柔らかな曲線を描いている薄紅色の唇に目がとまる。
この白い肌がほんのりと色付いたときの、艶やかな姿が目蓋に浮かぶ。
「……気をつけてよ、伊角さん」
「何が?」
「全部」
「何だよそれ」
きょとんとして瞬きを繰り返す伊角を見てため息がもれそうになる。
「だから、もっと警戒してって言ってんの。世の中アブナイことがいっぱいあるんだから」
大真面目で言ったというのに、伊角はプッと吹き出して笑った。
「和谷、一応俺の方が長く生きてるんだぞー。だいたい俺、男だよ。そんなに心配すんなって」
その言葉、全然説得力ねーんだよ、と胸の中で呟きつつ、あきらめたように和谷が言った。
「…あんまり飲み過ぎないでよ」
「わかってるよ」
本当は行かせたくなんかないのだけれど。
四六時中、側にいて監視しているわけにはいかないから。
それでも胸の奥で燻る、息を詰まらせるような独占欲。
和谷は畳についた伊角の手に自分の手をそっと重ねた。
ぴくりと動いた白い手を、そのままぎゅっと握る。
「ねえ、伊角さん。金曜の夜──帰りはウチに来てよ」
「……」
伊角の視線がすっと逸らされた。
「ダメ?」
沈黙を迷いととった和谷の声が幾分情けない響きを帯びる。
だが、すぐに思い違いを悟った。
「……最初からそのつもりだったんだけど」
薄らと頬を染めてボソリとつぶやいた伊角を、気がついたときには抱きしめていた。
そのまま唇を合わせると、腕の中の躯が微かに震えた。
直に感じる唇の甘さに、先程まで苦労して保っていた自制心が一瞬で吹き飛ぶ。
自分だけが感じることのできる、この甘い体温。
誰にも渡さない。
やんわりと押し戻そうとする手を捕らえてそのまま畳へと押し倒しながら、和谷が伊角の耳元
でささやいた。
「伊角さんが悪いんだぜ…そんな顔するから」
なんだよ、それ、と赤い顔で睨む伊角に、和谷は満足そうに微笑むと再び唇を重ねた。
「何だか嬉しそうじゃん、和谷」
棋院での手合いが終わり、自販機で買ったジュースを飲んでいた和谷は、知らずニヤけていた
頬を急いで引き締めた。
「そう?」
屈んで取り出し口から缶コーヒーを取った冴木が壁にもたれてプルトップを引き上げた。
「今日は伊角君は手合いなかったよな」
「うん、ないよ」
ウチで寝てる、とつい言いそうになって慌てて口をつぐむ。
伊角、の名に昨夜の記憶が鮮明に甦りかけ、上昇しそうになった体温を下げようとジュースを
ごくごくと飲み干した。
「あ、そうだ和谷。今度の金曜の夜って空いてる?」
その言葉に幸せ気分が一気に急降下する。
金曜の夜。
伊角の帰りを部屋でひとりで悶々としながら待つ自分の姿を想い描き、和谷は眉間に皺を寄せ
た。
「夜中まで、ガラ空き」
「…なんだよ、いきなり不機嫌だなぁ」
急に声が低くなった和谷を、冴木があきれたように眺めた。
「ほら、この間センセイの家で集まった帰りに今度みんなでメシでも食いに行こうって話になっ
ただろ? それ金曜なんてどうかなって言われてんだけど」
そういえばそんな話があったな、と和谷はすっかりふて腐れた頭で思い出していた。森下門下
の若手の棋士たちは皆仲が良く、時々そうした集まりがある。
ふと思い付いて、和谷は壁からガバッと身を起こした。
「冴木さん! そのメシ食う場所とかもう決まってんの!?」
掴み掛かりそうな勢いに、冴木が驚いて少し仰け反った。
「まだだけど?」
「7時に新宿の津田屋にして! お願いっ!」
「津田屋って…飲み屋でいいのか?」
怪訝そうに尋ねる冴木に、和谷が両手を合わせる。
「そこじゃないとダメなんだよ!」
「はぁ? まあ別にいいけど、おまえはジュースだからな。外で酒飲ましたのセンセイにバレた
ら大目玉だから」
「水でもいいからそこにして!」
変なヤツだな、とやはり怪訝そうにつぶやいた冴木は、それでも承諾して帰って行った。
食器の触れあう音と、賑やかな話し声。
金曜の夜ということだけあって店内は満席だった。
「こういうことね」
グラスを傾けながら冴木があきれたように肩をすくめ、隣で首を伸ばしては奥の座敷をちらち
らと覗く和谷の頭を小突く。
「ちょっとは落ち着けよ、和谷」
くすくすと笑われ、和谷は拗ねたように箸で唐揚げをつついた。
「おかしいと思ったんだよなぁ。どうせおまえ、この店来るのだって初めてなんだろ」
「…いいじゃん別に」
目の前に並んだ皿の料理を手当りしだいに口に放り込む。
冴木以外の仲間の酔いが進んでいるのをいいことに、和谷はロクに会話にも加わらずひたすら
もう一つのグループの方に注意を向けていた。
「あっちもだいぶ出来上がってきてるな」
和谷の心を読んだように冴木がからかうような視線をよこす。
「おもしろがってない? 冴木さん」
「当たり前だろ」
奥の座敷から一際大きな笑い声が上がり、和谷が再び首を伸ばす。
「何だかおまえ……まるで、恋でもしてるみたいだぜ」
あはは、と笑いながら投げられた言葉に、一瞬ドキリとする。
応えが遅れた和谷を特に気にするふうでもなく、冴木も同じ一隅に視線を向けた。
「ま、わからないでもないけどな。何か危なっかしいもんなぁ、伊角君」
「…そ、そうなんだよ」
冴木にわからぬようにホッと胸を撫で下ろした。
和谷としては伊角との関係がバレることに余り抵抗はないのだが、伊角が嫌がるために秘密に
するよう心掛けていた。
──アブナイ、アブナイ。
だがホッとしたのもつかの間、冴木の言葉に思わず立ち上がりそうになった。
「なあなあ、和谷。あの隣の学生みたいの。何だかさっきから伊角君にちょっかい出してるみた
いだぞ」
「え!?」
腰を浮かせて覗くと、見知らぬ男が伊角のすぐ隣に移動しているのが見えた。
九星会のメンバーではない。
伊角たちのいる奥の座敷には二つの長いテーブルが並べて置かれていて、片方は伊角たち九星
会、もう一方はどこかの学生らしきグループが陣取っていた。
学校がどうこうという言葉がしきりに聞こえてくるのでやはり大学生なのだろう。
離れているといっても同じ床続きのためたいした距離ではない。
そのためすっかり酔いが回った二つのグループは、歳が割と近いせいかいつの間にやら合同飲
み会のような様相を呈していた。
男ばかりの学生グループのテーブル側に九星会の女性陣が座っていたのも災いしたようだ。
先程の学生がテーブルに肘をつき、すぐ隣の伊角に親しげに笑いかけていた。
歳の割には手慣れた様子で、運ばれてきたグラスを伊角にすすめる。
最初はやんわりと断っていた伊角が上手くノセられてグラスを口に運ぶのが見えた。
それを満足げに眺める男を見て、和谷の頭に血が昇った。
「ふうん、伊角君、学生じゃないんだ?」
よく通る声が喧騒をぬって和谷の元まで届いた。
──気安く呼ぶなコノッ
剣呑とした視線を送るがもちろん気づくはずもない。
応える伊角の声はここまで聞こえなかったが、向かい側に座っていた九星会のメンバーが身を
乗り出すようにして何かを学生に告げていた。
「え、プロ!?」
驚きと賞賛の混じった学生の一際大きな声に、伊角がアルコールで上気した頬を更に染めてう
つむく。
──そんな顔、他の男に見せてんなよ伊角さんっ!
「和谷、和谷! こぼれてるって!」
冴木の声にはっと手元を見ると、飲みかけのウーロン茶がテーブルに小さな水たまりをつくっ
ていた。
「あ、やべ」
「そんなに気になるならちょっとあっちにまざって来たら? 知った顔も何人かいるんだし、一
応挨拶してあるんだしさ」
「んー…そうだけどさぁ…」
ふきんでテーブルをふきながら、和谷は曖昧に言葉を濁す。
向こうのグループとは店に着いたとき、「偶然」はち合わせたことにして、すでに声を掛け合
っている。低段者同士、手合いで顔を合わせているため見知らぬ間柄でもなかった。驚く伊角に
も「急にここでメシ食うことになってさ。驚いた?」などとバレバレの嘘を言ったら、あっさり
と信じられてしまい、和谷は「本当に俺より長く生きてんの?」と言いたいのを何とかこらえた
のだが。
側に行きたいのは山々だったが、それでは丸っきり嫉妬深い男の見本のようで躊躇してしまう。
こうして同じ店にいること自体どうか、という考えは和谷の頭からはすっぱり抜けていた。
そわそわし続ける和谷をよそに、奥の座敷では件の学生が伊角に何やらしきりに頼み込んでい
た。
はにかんでいる伊角を親しげに見つめる整った横顔。
大して歳もかわらないのであろうが、伊角よりもずっと大人っぽく見える。
悔しいけど、イイ男だ。
「…なんかアイツ、冴木さんに似てない?」
つい恨みがましい声が出た。
「えー、そうかぁ? 俺の方がイイ男だぜ?」
「……はいはい、そうでしょーとも」
おどける冴木に、これまた本当のことだけにちょっとだけムッとする。
「お? 即席囲碁教室が始まるみたいだぜ」
「え」
見ると、伊角と学生の前にマグネット式の携帯用碁盤が置かれていた。
「んなモン、持ってくんなよ九星会!」
「そういうおまえも持ってるだろ和谷…」
どうやら先程しきりに頼み込んでいたのはこれだったようだ。
──ホントは碁に興味なんか無いんじゃねぇの?
テーブルの上の小さな碁盤に身を寄せあうようにして座っているのが一層気にいらない。
学生は適当に相づちを打ちながら、その涼やかな瞳を細めて嬉しそうに伊角を見つめていた。
──やっぱ伊角さんのコトばっか見てんじゃねーか、アイツッ! 碁盤を見ろ、碁盤をっ!
「あーっ!?」
「なんだよ、和谷ウルサイなぁ」
「だって、ほらアイツ! どさくさにまぎれて手、握りやがった!」
質問するフリをしては碁石を動かす伊角の手に触れている。それだけでも和谷の怒りを十二分
に刺激しているというのに、彼は「目に入らない?」と言って伊角の前髪を梳いてみせた。
立ち上がりかけた和谷のシャツを冴木が掴む。
「落ち着けって。こんなとこで暴れるなよ」
「……わかってるよっ」
──だいたい触らせておく伊角さんも伊角さんだ! もっと警戒しろよ、わかってねぇなぁ!
伊角はそんな和谷の噛み付くような視線に気づく様子もなく、ひどく真面目な顔でマグネット
の石を並べている。接触過多な学生の行動も特に気にしていないようだった。受験直前の生徒に
勉強を教える家庭教師のような表情で石を置きながら何かを述べている。ここまで声は届いてこ
ないが、きっとひとつひとつバカ丁寧に説明しているに違いなかった。
伊角さんらしいナァ、と思ったら何やら急に力が抜け、和谷は一瞬学生への怒りを忘れた。
数メートル先で碁盤に視線を落とす姿を、愛しげに見つめる。
生真面目な表情と、アルコールで上気した頬。
そのちぐはぐな組み合わせが生み出す、えも言われぬ艶やかさ。
ウーロン茶しか飲んでいないのに躯がカッと熱くなるのを感じて和谷は慌てた。
──こんな所で何考えてんだ、俺はっ!
酔ったように頬が紅潮する。
ごまかすように特別食べたくもない冷や奴をかき込んだとたん気管に入ってしまい、盛大にむ
せかえった。
「おいおい、大丈夫か?」
冴木の声はあきれを通り越してすでに憐れみの色を帯びていた。
やっと落ち着いた和谷が目に滲んだ涙を拭きながら奥の座席を見ると、伊角の姿がなかった。
和谷の視線に気づいた冴木が店の出口付近を指差す。
「さっきあっちに行ったよ。トイレだろ」
あ、そっか、と箸を持ち直して料理に手を伸ばそうとした和谷の動きが止まった。
視界の隅をよぎった影を目で追う。
伊角にべたべたとくっついていた、あの学生だった。
たいして酔っていないのか、しっかりとした足どりで通路を通って行く。
──アイツもトイレか。
和谷の視線には気づいていないようだった。
ずっと座っていたのでわからなかったが、こうして見ると結構背が高い。しかも脚の占める割
合が嫌味なほど高い。
OLらしき女の子たちが横を通り過ぎて行った彼を指差し、きゃあきゃあとはしゃいでいるのが
見えた。
──ちょっかい出すならあっちにしろよなー。
おもしろくない気分で飲んだウーロン茶は一層にがかった。
再び料理に箸を伸ばして口に放り込む。
少なくとも見た目は文句無しにイイ男だった。
きっと気のきいた言葉も料理の美味しい店もいいデートスポットもたくさん知っているに違い
ない。和谷よりもはるかに。
キスするときにちょっと背を伸ばしたり、なんてことは絶対に、ない。
──伊角さん、グラッとなんかしないよな…?
自分でも何を馬鹿なことを、と思いつつも灰色の靄のようなものがチラリと頭の隅をよぎる。
ノルマのように箸を動かし続けたが、味なんてわからなかった。
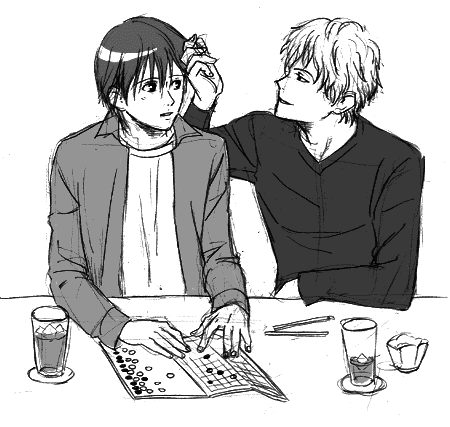
illustration by HIBANA KUSAKA sama : Various fever
>> 2
|
|
|